| |
|
|
2017年12月5日(火)開催。 当日参加者11名。申込14名。
豊臣秀吉と明智光秀が天下分け目の戦の舞台となった天王山をいただく風光明媚な場所です。大山崎は京の玄関口として栄えたところです。
貞観年間(859年)に神官が神示を受けて「長木」(てこを応用した搾油器)を発明し,
荏胡麻(えごま)油の製造が始まったことから、日本における製油発祥地とされる。
その後,「大山崎油座」の制度で荏胡麻油の販売権を独占して、多くの兵火に焼かれながらも江戸時代まで栄えた。しかし、幕末「禁門の変」時に長州藩屯所が山崎にあったため、攻撃を受けて多くの商家とともに焼失し現在に至っています。
大山崎の地は木津・宇治・桂川の三川合流で江戸時代までは交通の要所として栄え、長岡宮遷都では難波宮から資材を運んだであろうし、土佐日記の作者である紀貫之も大山崎の津からこの地を訪れています。
秋の紅葉も素晴らしく花見の残り福かなと思われます。また、最近では天皇ご夫妻が聴竹居にも足を運ばれています。
大山崎ボランティアガイドさんの説明を聞きながら歩きました。
<離宮八幡宮>
荏胡麻(えごま)油発祥地で油の製造と販売の中心「油座」として栄えていました。
現在は油の神様として親しまれています。
<関大明神>
山城の国(現京都府)と摂津の国(現大阪府)との府境に建つ神社。古代の関所「山崎関」跡といわれている。
<山崎聖天(観音寺)>
住友家、三井家など巨大豪商の援助を得て聖徳太子の作と伝えられる十一面千手観世音菩薩を本尊とし中興開山された。以降、歓喜天(かんぎてん)を祀り、霊元、東山、中御門天皇の厚い帰依と商売繁盛・家運隆昌を願う住友家、鴻池家、三井家などの信仰や、京都、堺など商人の参詣を得て大いに発展した。こうしたことで本尊の十一面千手観音菩薩よりも
歓喜天の信仰で賑わい、「山崎の聖天さん」として知られるようになった。
<聴竹居>
建築家・藤井厚二の設計により彼の自宅として建てられた実験住宅。
エコを先取りした優れた建築で日本の近代建築20選の建物に選ばれています。
日本の代表的な環境共生住宅です。2014年6月に天皇陛下ご夫妻も京都滞在中に希望され視察されました。
|
離宮八幡宮の建物
 |
|
関大明神は山城の国(現京都府)と摂津の国(現大阪府)
との府境に建つ神社。古代の関所「山崎関」跡
 |
あらゆるご利益があるとされる
歓喜天(かんぎてん)を祀る建物
 |
|
山崎聖天の紅葉はまだ綺麗でした
 |
藤井厚二の実験住宅は建物に色々と工夫がされ、エコの先取りもされた内部と
日本で当時6台しかない冷蔵庫(2000萬はするであろう)スイス製など電化が進む
  |
聴竹居の庭で残り福の紅葉も素晴らしくハイポーズ
 |
|
国宝待庵の茶室がある妙喜庵
 |
| |
|
|
(運営委員 川崎泰弘 記す) 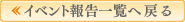 |

