| |
|
|
2017年06月15日(木)開催。 当日参加者9名。申込10名。
真言宗の宗祖・弘法大師と中興の祖・興教大師覚鑁のご誕生を祝う恒例行事。
ほら貝が鳴り響く中、真言を唱え、営なわれる法要は感動ものでした。
大峰山入峰の修験者の柴灯大護摩供養で煙をかぶるとご利益があるとのこと
こんなまつりは初めてだと絶賛
弘法大師は、中国に渡り日本に密教を伝え、高野山を開いた方です。真言宗の宗祖であると同様に、さまざまな業績を残され全国各地で尊崇されています。
興教大師は、弘法大師の教えを復興したことから、真言宗の中興の祖といわれる方です。
弘法大師のご生誕は宝亀5年(774年)6月15日、興教大師のご生誕は嘉保2年(1095年)6月17日です。ちょうどお二人が生まれた六月が緑の美しい季節ですので、このお祝いを「青葉まつり」といいます。
<智積院>
豊臣秀吉の愛児鶴松の菩提を弔うために建立した祥雲禅寺の寺域を徳川家康が寄進し、五百佛
山根来寺智積院と改め、仏教研学の道場として栄えた。
江戸初期を代表とする池泉回遊式庭園は、中国廬山を形どっているといわれて利休好みの庭と言
われている。
長谷川等伯一派による楓図、桜図(国宝)極彩色の障壁画を展示。
桜図は長谷川等伯の長男・久蔵が描き素晴らしいものでした。
<養源院>
浅井家の菩提寺。中には、教科書に出てくる俵屋宗達作の「白象」「麒麟」「獅子」が見られ、徳川家康が伏見城を去るとき守護した鳥居氏の切腹した血の血天井がありました
|
大峰山から駆けつけた修験者(山伏)や智積院末寺から応援の僧のお練り行列
  |
各種法要のための行事をこなしているところ
  |
柴灯大護摩供養のため柴の下から
護摩木を燃やしている。
水をかけてくすぶる様にしていた。
 |
|
ご利益の煙を大きな団扇で方々に煙が行くようにした。
まるで煙で燻される様でした。
 |
利休好みの智積院の庭
 |
|
智積院の門前で記念撮影
 |
| |
|
|
(運営委員 川崎泰弘 記す) 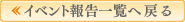 |

